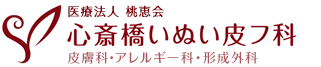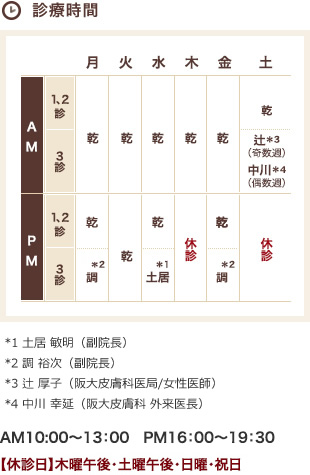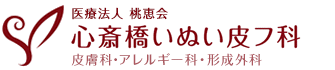- ブログテーマ一覧
- アーカイブ
-
- 2024年11月 (7)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (3)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (6)
- 2024年5月 (5)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (6)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (3)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (2)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (3)
- 2022年6月 (2)
- 2022年3月 (3)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (8)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (6)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (5)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (2)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (3)
- 2019年9月 (4)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (4)
- 2019年6月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (3)
- 2018年8月 (2)
- 2018年7月 (2)
- 2018年6月 (5)
- 2018年5月 (3)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (7)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (2)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (2)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (5)
- 2016年6月 (9)
- 2016年5月 (3)
- 2016年4月 (6)
論文評(2):村田洋三,「乳房外 Paget病の臨床・病理相関(皮膚の科学17:299-3112)」を読んで
尊敬する皮膚腫瘍研究者であられる村田洋三先生の総説です。
2000年代に入って病変部周辺を広く生検するmapping biopsyを行って乳房外 Paget病の切除範囲を決めるのが半ばルーティンのようになりました。当時卒後10年目ごろであったわたしは「あれ?今までそんなことしなくても1-2cm離して切除すれば、そんなに再発はなかったぞ」と思いながら、「皮膚腫瘍の専門Drがやっているんだから、そうなのなかあ」と思い、阪大病院病棟でもしばしば施行されるのをみていました。本論文で村田先生は自験例の詳細な観察により<きっきり臨床像を捉えればmapping biopsyは必要ない>ことを明確に示されています。またmapping biopsyの基礎になった論文はアメリカのある病院のデータに基づくものですが、その論文について<方法論がきちんと述べられていない。きっちり臨床像(臨床的皮疹の境界)を取っていないからmapping biopsyが必要になる>という趣旨を述べておられます。村田先生、なるほどそういうことなんですね!
わたしが卒業後入局した当時の阪大皮膚科・形成外科の先輩たちは卓越した臨床力を持っていたから、乳房外 Paget病の再発例をめったと経験しなかったのだと今更ながら気づき感銘しています。
村田先生は自験数例の臨床像と病理像を相関させて見事に結論を導いておられます。もしかしたら、いい加減な多数例報告より確実な少数例の観察の方がエビデンスとしては重きをなすという、EBMへのラディカルな挑戦状なのかもしれません。